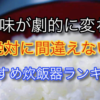【書評】『ソラリス』SFの大傑作を新訳で読んでみた!映画と印象が違いすぎるがどっちも良い

こんにちは。
学生時代にアンドレイ・タルコフスキーの「惑星ソラリス」を観て衝撃を受けたsasaki(@sasaki_holiday)です。
今回、ご紹介する1冊はスタニスワフ・レムの「ソラリス」です。
ソラリスは言わずと知れたSF小説の大傑作ですが、元々「ソラリスの陽のもとに」という邦題で翻訳されていました。
この「ソラリスの陽のもとに」は元がポーランド語で書かれた原典をロシア語版からの重訳でした。
さらに当時はソ連の検閲などにより多くの部分がカットされて出版されていました。
つまり、重訳であるがゆえに原典の微妙なニュアンスが訳しきれていなかったり、検閲の対象となった部分が取り除かれたものでした。
しかし、2015年に沼野充義さんによるポーランド語版からの新訳がハヤカワ文庫SFより刊行されました。
そんなソラリスの完全翻訳版を今回は改めて読んでみたので感想とか感じたこと、あとは映画「惑星ソラリス」との違いなどを読み解いていきます。
簡単なあらすじ
まずは、ザックリと登場人物とあらすじ紹介。
ちなみにあらすじは簡単にではありますが、ラストまでの流れを書いているので初見の方は注意です。
主な登場人物
- ケルヴィン:主人公。心理学者でソラリスの研究者。
- スナウト:ケルヴィンより先にソラリスに到着していた研究者
- サルトリウス:こちらもケルヴィンより先にソラリスに到着していた研究者
- ハリー:ケルヴィンの元恋人
あらすじ
舞台は知的な活動を示しながらもその仕組みや動機は不明で数多くの研究が繰り返されている惑星「ソラリス」
ソラリスの大半は知的な活動(模倣や創出)をおこなう海でおおわれている。
ソラリスの研究ステーションに到着した主人公ケルヴィンはステーションの異様な様子に気が付く。
ステーション内には本来存在するはずのない人間が出現するという現象が起きていた。
そのことがキッカケで自殺を図った研究員や部屋に閉じこもっているサルトリウス。
唯一会話ができるスナウトでさえも事情を把握できていないケルヴィンとは会話が成立しない状況。
そして、ケルヴィンがステーション内の自室で目を覚ますとそこに現れたのは数年前に自殺したはずの元恋人ハリー。
仕草やしゃべり方、二人だけしか知らない思い出など見た目や中身もハリーそのまま。
この客人(思い出の人物)はソラリスの海がケルヴィン達の記憶から作り出したコピーであった。
ケルヴィンは次第にこの客人によって精神を蝕まれていく一方で好意を抱くようになる。
一方で、スナウトとサルトリウスはこの客人を破壊する方法を見つけ出す。
ハリーはケルヴィンと過ごしていく中で自分がソラリスの海によって作り出されたコピーであることに気が付き自らを破壊しようとする。
ソラリスの海はなぜ、客人を送り込み、どんな結果を期待していたのかは分からないがケルヴィンはハリーを再び失ったソラリスに残ることを決意する。
新訳ソラリスを読んだ感想
はい、とまぁこんな感じのお話なんですわ。
ザックリあらすじだけ追っていくと、結構王道なSFの設定に宇宙でのラブロマンス的な要素とホラー的な要素が入り混じったお話ですね。
ですが、実際に読んでみるとそんな生易しいもんじゃないんです(笑)
まず、ソラリスのSFとしての重厚感を生み出しているのがメタ的な要素。
あたかもホントにソラリスという惑星が存在してそれを研究してる学者が多くいて、それぞれに異なる主張が時代を追って生まれては消えているかのような描写がすさまじいです。
実際に多くの論文が発表されているんじゃないかと錯覚するほどです。
逆に本筋の話だけ追っていきたい人にとっては邪魔に感じるレベルです(笑)
で、過去の翻訳版ではこの辺の描写が結構削られていたみたい。
というのも、旧ソ連の骨格となっていた「科学」に対する否定や矛盾みたいな部分をつっつくような内容や神と人間のあり方までソラリスという架空の惑星を中心に語られています。
しかし、今回読んだ新訳版ではその辺がノーカットで描写されています。
だからSFとしての深みとリアリティが段違いです。
続いてこのソラリスが傑作である理由として感じるのが未知とのコンタクトの捉え方です。
一般的なSF映画などでは地球外における「未知」というと宇宙人、エイリアンあたりですよね。
どうしても、地球外の知的生命体とは言ってもどこか人間的な特徴を備えていて彼らにも文化があります。
しかし、ソラリスにおける未知は「海」なんです。
広大で一見無機質に見えるけれど、知的な活動は行われている。
しかしその意図や目的は人間が理解し得る範疇にはない。
けれどやはり、ソラリスの海は確かに知的な活動を行っているという事実のみが存在する。
どうしても人類が遭遇してコンタクトを取る対象というとどこか生物としての面影が残されて描かれる場合が多いですが、ソラリスは違います。
さらに大概の場合、人類が未知と遭遇した場合のテンプレは「友好関係を結ぶ」「侵略する」「侵略される」のどれかだと思います。
しかし、ソラリスはただそこに存在しているだけです。
でも考えてみてください。
実際、今後人類が遭遇し得る知的な物体が必ずしも人間と同じ概念に存在しているなんてことないじゃないですか。
もしかしたら、明らかに何かの意図をもって活動している空気かもしれないし。
後述しますが、最初この作品を映画で観たときはあくまでコンタクトの対象は海が作り出した客人(ハリー)なんだと思っていました。
でも違います。あくまでこの作品における未知は海であり、ハリーは海がその活動の一環で生み出したモノでしかないんです。
そこには確かに海の活動における意図や目的はあるかもしれないが、そんなものは人間の解釈に過ぎず、結局は海に意思があるかどうかなんてのも人間の理解の範囲内なんですよ。
この辺がこれまで散々、ソラリス学の様々な考え方が本文中で語られてきますが一種の皮肉というか(笑)
タルコフスキーの「惑星ソラリス」と印象が違いすぎ!
そして、この新訳版「ソラリス」を読んでみて感じたことは映画「惑星ソラリス」との決定的な違いです。
冒頭でもチラッと話しましたが、私は学生時代にタルコフスキーの「惑星ソラリス」を観て衝撃を受けた記憶があります。
SFというには有機的な美しさで描かれるソラリスと得体の知れない異質な存在と頭では理解しつつもハリーに惹かれていくケルヴィンの姿。
どこか詩を読んでいるかのような感覚でした。
で個人的にもかなり好きな映画の一つなんですが、小説を改めて読んでかなり印象が違うことに驚きました。
そして、スタニスワフ・レムの「ソラリス」が大好きになりました。
なぜか。
そもそもそれぞれの主題が違うんです。
タルコフスキーの「惑星ソラリス」は美しく幻想的な惑星ソラリスでケルヴィンの記憶から決して消えない負の記憶である「ハリー」に自責の念と葛藤しながらも心惹かれる様子が不気味でありながらも美しく描かれています。
ここで主題となるのは「地球外での切ないラブロマンス」って感じでしょうか。
一方で、スタニスワフ・レムの「ソラリス」は人間という枠を超えた未知とのコンタクト。
これに尽きると思います。
タルコフスキーはソラリスという舞台を使って人間の理解の範囲内のお話(過去のトラウマ・恋愛)を極限まで美しく表現しました。
レムは人間の理解を超えたソラリスという惑星と人間が対峙したときの儚さや虚無感などを表現しているように感じます。
じゃあ、どちらが映画向きかといえば間違いなくタルコフスキーの「惑星ソラリス」でしょう。
しかし、レムの「ソラリス」にはSFの軸となる「科学」という人間の英知を超えた概念と人間が出会うストーリーが描かれています。
そう考えると、レムがタルコフスキーの映画に全く納得がいってなかったってエピソードも納得(笑)
だって描いてるものが違うんだもん。
新訳版「ソラリス」まとめ
というわけで今回は、SFの大傑作スタニスワフ・レムの「ソラリス」の完全翻訳版を読んでみた感想とか、映画版との感じ方の違いとかを書いてみました。
よくタルコフスキーの映画版ですら難解な作品と思われがちですが、全くそんなことはないと思います。
むしろ、そもそもが人間に理解できないもののお話なのでそれぞれがどう感じるかの作品だと思います。
個人的にはタルコフスキーの「惑星ソラリス」が好きだっただけに小説の読破後はある意味で衝撃でした。
特に今回の新訳版を読むと、本質的にタルコフスキーの映画版とは描いているものが違うことが実感できます。
ぜひ、興味のある方は読んでみてはいかがでしょうか?
以上、ご精読ありがとうございました。